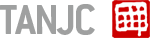東南アジアの現代美術が
「語りかけ」から「会話」へ
(本稿は某学会誌からの依頼で執筆したものを転載しています)
このたび、東南アジアの現代美術についてのリポートをリクエストされたときに、私の頭に思い浮かんだのは特定の作品の情景ではなく、会話を求める作家の真っ正面の顔だった。ここで紹介するに値する作品がないわけではないが、モチーフや表面のビジュアル的な要素よりも、東南アジアの現代美術が私に与えた印象は、作者が会話を求めるその姿勢にあるからだ。
96年に来日して以来、私は首都圏の美術館を始め、宇都宮美術館や福岡アジア美術館でたびたび多くの東南アジア作品に触れてきた。当時は偶然とは思えないほど、キャンヴァスに映し出される絵のほとんどが戦争の悲惨さ、紛争や貧困生活だった。過剰な被害妄想さえ思わせるおびただしい作品数で、痛々しくて直視することすらできなかった。もちろん紛争や内戦を含めて第二次世界大戦などそれぞれは歴史上の出来事として事実であり、目を背けるべきではない。被害者がキャンヴァスを媒体に、加害者や傍観する者に向けて静かに叫んでいるように思えた。また当時、それらの作品ばかりが日本の美術界で取り上げられたわけは、教科書の改ざんに対する些細な埋め合わせ、あるいは謝罪だったのかもしれない。終戦60周年の契機に公開された戦時中の日本絵画も含めて、報道写真の代わりに画家の表現というフィルタを通して描かれる戦争が日本の観客にとって程よいリアリティを帯びた副次的な教科書となったのかもしれない。
これまでの10年間、現代美術の新生なアーティストのほとんどが戦争を実体験していない世代であるためか、被害者としてのアプローチが次第に美術館から消えていった。教科書のように一方的に語りかける形態から少し変わってゆく。国家の急速な近代化に伴う経済格差に生まれた農村の貧困や、都市生活の西洋化に対する違和感などプロテスト(異議申し立て)の表現が続々と登場する。それはただの叫びから、同じ境遇にいるもの同士との会話に変わりつつある動きとして私はとらえた。
しかし、公害による環境破壊の問題など後期資本主義に対する生活者サイドからの批判表現はもはや東南アジアの第三国の特有なテーマではないことをも、彼らは次第に気づいていったのだろう。あるアーティストが自民族意識に目覚め、儀式や紋様のような伝統文化を再生するような作品をポップな作法で提示することも多く見うけられるようになった。これもまた、グローバリズム化する美術の中で自らのアイデンティティを売りにする戦略として明らかに賢明であろう。
西欧近代から現代にかけての表現に慣らされている日本人の目から見ると、東南アジアの表現はいかにも素朴な力強さに溢れている。西欧近代主義の到来が日本より数十年も遅れた彼らの表現は、農業生産物の一次産品を生産する手つきのようだ。われわれの遠い記憶の層を時にヴィヴィッドに穿つような力がある。また、それらを取り上げるキュレーターは、マッサージのような消費活動のように、日本人が失った伝統文化による「癒し」をエキゾチックな作品を介して機能させたような気がした。同じアジア人でありながら距離感を覚えた我々に、そんな作品がエキゾチシズム(異国情緒)を媒体に会話を誘うのに意欲的なところが、私にとってもっとも印象的なのである。
西欧近代を曲解し、表層的に模倣した拝欧主義とエスニックな面を強調するニューオリエンタリズムの二項対立からアジア地域の美術が抜け出し、世界中の人々と共にする同一の地平に立つためにアーティストたちは表現の題材を工夫するようになったようだ。お互いの立ち位置を新たに仕掛けられたのは会話を促すためなのだ。
シンガポールのアマンダ・ヘンの作品「もうひとりの女」に出会ったときに、私は衝撃を受けた。いかにも東南アジア人肌をした母娘が裸で抱き合うなどパフォーマンスを写真に撮った作品だった。40歳になっても自分の母親との関係をうまく作れないアマンダは、母親といっしょに作品を作ることで、母親との間に絆を結ぼうとした。人は誰でも母親の子供なのだから、母親に理解してもらいたいという欲求は、おそらくもっとも根源的なコミュニケーション欲求なのであろう。そんな基礎的な会話への回帰と同時に、地元の中国系家父長制イデオロギーの束縛を暗示したアマンダは女性も男性も、そして異民族をもこの会話に誘い込んだ。作者のそのような真っ正面の顔を私たちは見た。
今日、東南アジアで新しく生まれているアートの多くは異文化環境においてもより親しみやすく関連性を見出すことの容易さを求めている。ポスト植民地の国家的アイデンティティ、文化財、変化し続ける環境、コミュニティ、宗教、近代化およびグローバル化の影響、そして西側外交政策といった諸問題の表現を媒体に、世界の大規模なコミュニティでの会話へと繋がっていこうとするのである。アートを媒介した会話への欲求が活気に溢れる活動の推進力になっていることを、今盛大に開かれた第1回シンガポールビエンナーレも裏付けているのではないかと思う。
2015年10月15日