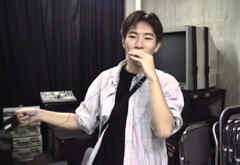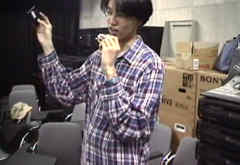|
2000年10月20日 (金曜日)
4:00PM 〜 5:15PM
場所:芸工大映像演習室E
人数:7人 (クラスメート)
第1回実験はFM発信機試作機1号(回路が裸で電池をテープで固定されている状態)を使って決行されていました。
説明がなれていなくて、言葉がつまり、でも実験参加者みんな映像コースの生徒ということで、 理解が早かった。
始まって、まだ何も命令してなくても、みんな通信し始めて、知っている人の声が確認できたりしました。 ラジオの電源を入れることさえ分かっていない関口さんが「何も聞こえない」と…
●実験者の多元化に気づき「扱いやすさ」を考える
電波状況悪くて、ノイズしか聞こえない人も出てきます。 ラジオ向きを変えたりして体を動かす現象がおかしくて面白かった。 一定のチャンネルに設定したつもりであっても、お互いの位置関係で干渉し合って周波数が歪んでいる。
その場でラジオチャンネルを微調整して聞こうとすると別の人の電波が入って来たりして混乱します。やめておきます。
●自分が聞いている声が誰なのか確認はできても、自分の声は誰に行っているのか気にしていません。
なのに、みんなはマイクに向けて一生懸命「もしもし、あ〜」と発声しっぱなし。聞いている声に答えている。 武士は機械に強いおかげか、冷静に全体の場を見ていて「生の声が聞こえないようにしゃべらないと」と発言。
●生声で聞こえないよう注意
私が実験者1人ひとりに「誰の声を聞こえる?」と聞き、「彼の」、「多分彼女の」と言った答え。 続き「自分の声は誰が聞こえているのか分かる?」と聞いたら、「いやぁ〜分からない…おい!誰か私の声を?」と。
寺島さんが「私がオイと言ったら3秒後オイと言ってくれれば分かると思う」と相手から生の声で返事を求めようとしていました。 自分の声が誰に行っているのか確認し始める参加者たちは、言葉遣いの面白さに焦点を絞った。
●「もしもし」という掛け声が目立つ。
「私の声聞こえているのは誰?」と丹念に言葉で返事を求めながら、現場のほかの参加者の反応を観察している。
この時点で「自分が聞こえている声の持ち主の後ろに立って、例えば武士の声が聞こえるなら武士の後ろに立って並ぶ」と。
●後ろに立つという意味が最初にピンと来ない人が意外と多い。言い方を考える。
みんな並べ始めるが、2人が同時に武士くんの声が聞こえているので2列になった。 井本くんと武士くんがお互いに声が聞こえるので、お互いの後ろに並ぼうとして、グルグル廻り始めた!
|